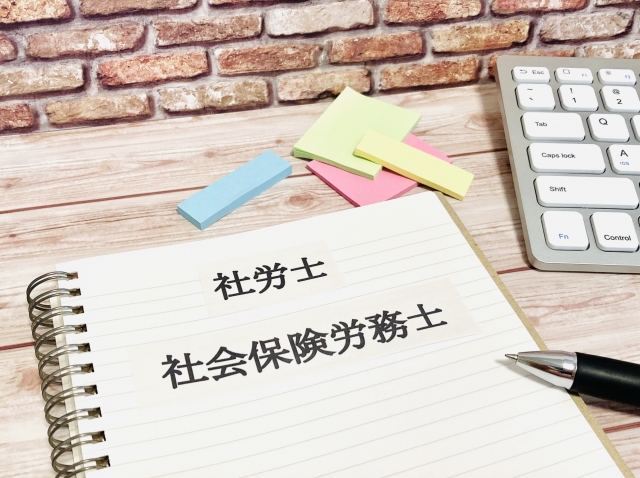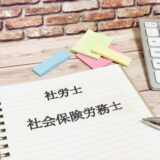こんにちは。「社労士事務所開業への道」ブログ管理人のみやびです。
社労士試験が終わり、最近は心が少し落ち着いてきました。
しかし、昨日、ちょっとした事件が発生しました!その事件についてお伝えします。
今回の試験対策では、TAC社労士講座(通信)を受講しました。一般教育訓練給付の対象講座です。
私は「講座のWEB視聴が8/31まで=講座終了日も8/31」と思い込んでいたのですが、
そろそろ申請にいこうかな、教育訓練修了証明書を見てみると、
講座終了日はなんと8/4!
ということは、支給申請は「訓練終了日の翌日から1か月以内」なので、
期限ギリギリ!慌ててハローワークへ駆け込みました。
当日の動きと持参書類
郵送も可能なようですが、締切直前だったので窓口申請を選択。
受付で「教育訓練給付の申請です」と伝えると、受付の方が少し戸惑った表情をされて焦りました。
仕事ができそうなお兄さんスタッフが代わりに対応してくれ、
ほどなく、雇用保険のブースへ案内されました。
教育訓練給付の支給申請は、窓口に直接申請に来る人は少ないってことかもしれません。
以下の申請書類を準備し、確認して頂きました。
- 教育訓練給付金支給申請書:TACが印刷したものを修了証明書とともに同封してくれていました。必要事項を記入。
雇用保険被保険者番号が必要です! - 教育訓練修了証明書
- 領収書:クレカ払いでしたが、修了証明書とともにクレカ用の領収書が同封されていました。
- 教育訓練経費等確認書:厚労省サイトからDL→印刷→自分で記入しました。
- マイナンバーカード(原本):窓口では、原本確認、郵送ならコピーで送付するようです。
- 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード:キャッシュカード原本を準備していましたが、以前の雇用保険受給の際の口座が登録されており確認はスムーズでした。郵送では、コピーを同封するようです。
退職日の関係で支給要件を満たすかどうか不安でしたが、その旨を伝えると、
端末でささっと照会→「要件を満たしています」の印字資料をその場で提示してくれました。
なんだかんだで、約5分で手続き完了できました。
「1か月以内に振り込みが行われる」との案内を受け、胸をなでおろしました。
教訓:「視聴期限」と「講座終了日」は別物。修了証明書の終了日を必ず確認し、翌日起算1か月を厳守しましょう。
本日の学習:労働保険徴収法
今日は労働保険徴収法から、趣旨に関する過去問をピックアップします。
<択一式対策 一問一答(過去問より)> ~趣旨~
① R2-雇8D
労働保険徴収法は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めている。
答え:〇 法1条 設問の通り正しい。
「この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする」とされている。
② R6-雇8B
都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業については、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係の双方を一の事業についての労働保険の保険関係として取り扱い、一般保険料の算定、納付等の手続を一元的に処理する事業として定められている。
答え:× 法39条1項、則70条1号
設問の「都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業」は、同項の厚生労働省令で定める事業に該当し、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係の双方を別個の事業についての労働保険の保険関係として取り扱い、一般保険料の算定、納付等の手続を二元的に処理する事業となる。
(厚生労働省令で定める事業:二元適用事業)
・都道府県および市町村の行う事業/都道府県に準ずるもの・市町村に準ずるものの行う事業
・港湾労働法2条2号の港湾運送の行為を行う事業
・雇用保険法附則2条1項各号の事業(農林・畜産・養蚕・水産(船員が雇用される事業を除く))
・建設の事業
おわりに(小さな振り返り)
学習も手続きも、「期日」と「定義」の確認が命。教育訓練給付は修了日の翌日起算1か月、徴収法は一元/二元の区分を言い換えで出されがちです。今日のインプットを短時間のアウトプット(穴埋め・一問一答)で固定化して、次に進みましょう。