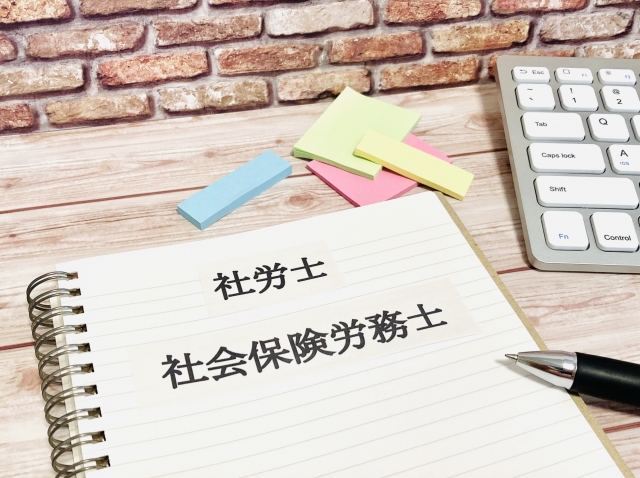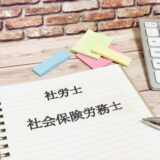みなさん、こんにちは。
「社労士事務所開業への道」ブログ管理人のみやびです。
今回は雇用保険法の目的条文と適用事業についてです。
目的条文は選択式で狙われやすい鉄板パート。語句レベルで暗記しておくと本番で強みになります。
適用事業については、過去問を載せてみました。
穴埋め問題
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について( A )となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が( B )職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び( C )をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の( D )を図るとともに、( E )を容易にする等その( F )し、あわせて、労働者の( G )に資するため、( H )、( I )及び( J )、労働者の( K )その他労働者の( L )を図ることを目的とする。
答え
- A:雇用の継続が困難
- B:自ら
- C:所定労働時間を短縮することによる就業
- D:生活及び雇用の安定
- E:求職活動
- F:就職を促進
- G:職業の安定
- H:失業の予防
- I:雇用状態の是正
- J:雇用機会の増大
- K:能力の開発及び向上
- L:福祉の増進
暗記のコツは「雇用の継続が困難」「自ら」「所定労働時間を短縮することによる就業」といった新しいフレーズを確実に押さえることです。試験本番ではこれらが穴埋め候補として狙われやすい部分です。
<択一式対策 一問一答(過去問より)>
~適用事業~
① R4-2E
事業とは、経営上一体をなす本店、支店、工場等を総合した企業そのものを指す。
答え
× 行政手引20002
雇用保険において、事業とは、経営上一体をなす本店、支店、工場等を総合した企業そのものを指すのではなく、個々の本店、支店、工場、鉱山、事務所のように、一つの経営組織として独立性をもった経営体をいう。
この「事業」の概念は、徴収法にいう「事業」の概念と同様である」とされている。
② R4-2B
建設の事業が労働保険徴収法第8条による請負事業の一括が行われた場合、被保険者に関する届出は元請負人が一括して処理しなければならない。
答え
× 行政手引20002
雇用保険に係る保険関係及び労災保険に係る保険関係の成立している事業のうち建設の事業については、徴収法第8条の規定による請負事業の一括が行われた場合であっても、被保険者に関する届出の事務等、法の規定に基づく事務については、元請負人、下請負人がそれぞれ別個の事業主として処理しなければならない。
③ H30-7ア
適用事業の事業主は、雇用保険の被保険者に関する届出を事業所ごとに行うが、本社で事業所ごとに書類を作成し、事業主名で届出できる。
答え
〇 則3条、行政手引22001
本社において事業所ごとに書類を作成し、事業主自らの名をもって提出することができる。
現実の事務を行う場所が個々の事業所である必要はなく、例えば、本社において事業所ごとに書類を作成し、事業主自らの名をもって提出することは差し支えない。この場合には、各届書の事業所欄には必ず個々の事業所の所在地を記載し、事業主住所氏名欄には、その本社の所在地及び事業主の氏名を記載するもの、とされている。
④ H30-7イ
適用事業部門と任意適用事業部門を兼営している場合、全ての部門が適用事業となる。
答え
× 行政手引20106
設問の場合、それぞれの部門が独立した事業と認められるときは、適用事業に該当する部門「のみ」が適用事業となる。
⑤ H30-7ウ
雇用保険法の適用を受けない労働者のみを雇用する事業主の事業は、常時5人以下であれば任意適用事業となる。
答え
× 法5条1項ほか、行政手引20105
任意適用事業(暫定任意適用事業)となるのは、常時5人未満の労働者を雇用する個人経営の農林水産の事業(船員が雇用される事業を除く)である。また、雇用保険法においては、労働者が雇用される事業を適用事業とするとされており、雇用保険法の適用を受けない労働者のみを雇用する事業主の事業については、その数のいかんにかかわらず、適用事業として取り扱う必要はないとされている。
条文は語句で覚えるのがコツ。穴埋めや一問一答を繰り返すことで定着します。
次回は、労働保険徴収法を取り上げます。